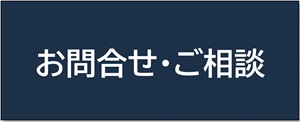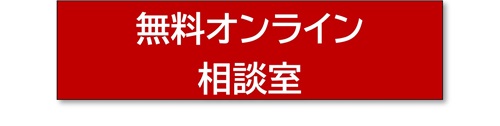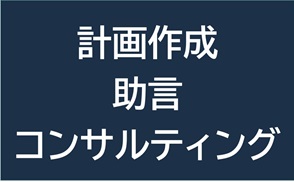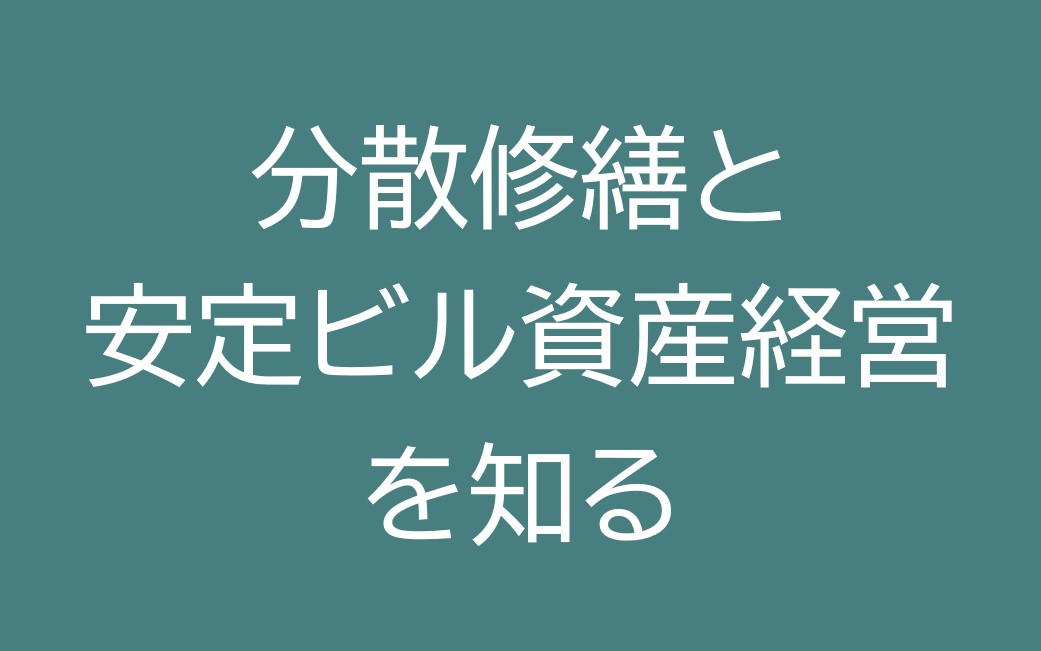日本全国の地方自治体様向け
.
地方自治体様向け
縮小日本の「街の持続」取り組み
時代はもはや街作り=再開発ではありません。誰も取り残さない、現在の街の住民を大切にする街の持続の時代です。
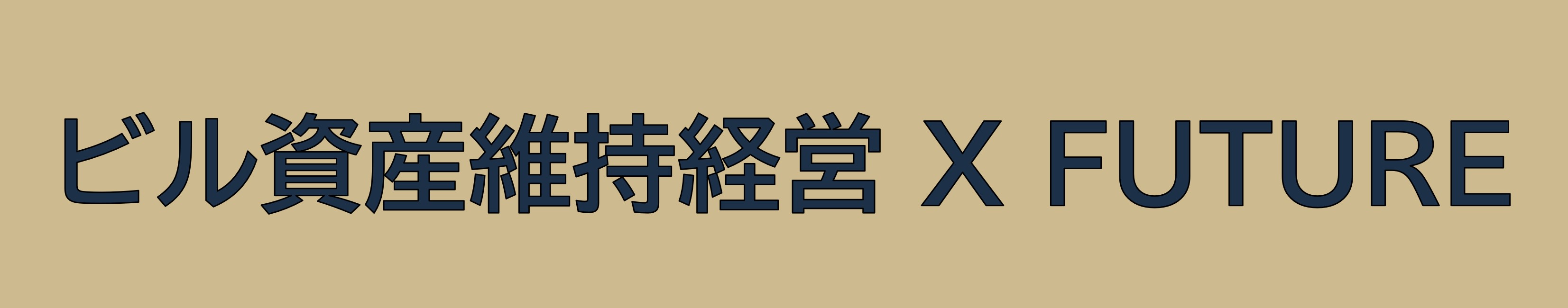
近年持続可能な街づくりが言われるようになりましたが、昭和のスクラップアンドビルド発想である限り、ごくわずかな対象地区以外は取り残されます。コンパクトシティー化もいわれますが、どうして、他人の土地やその地区の歴史を安易に抹殺して良いのでしょうか?
人口が減少してゆく現在、建替えや再開発ができる地域は、どんどん限られてきます。
人口激増地価右肩上がりの時代ではないという事は、今までのように
-
デベロッパーのビジネスありき
-
不動産業者のビジネスありき
-
建設業界・建築士のビジネスありき
-
行政の街作り政策ありき
では、資金力が弱い街の建物所有者達が、どんどん取り残されるという事です。
人口激減時代の今、街に本当に必要なのは、「減少した市民を置き去りにしない」「誰も取り残さない」事ではないでしょうか?でなければ一体誰のための、「持続可能な街作り」でしょうか?

■誰も取り残さない現在の街の持続とは
誰も取り残さない現在の街の持続とは、現在の建物や住宅が建つ街の持続です。既既にある街の持続とは、現在の街の住民が、生活とビジネスの基盤を失わない事です。にある街の持続とは、現在の街のビルやマンション戸建ての廃墟を増やさない事です。
既にある街の持続とは、つまり現在街に建つ建物や住宅が適切に延命されて存続する事です。それも無理のない低予算で、現在の建物を長寿化出来る事です。その実現に必要なのは、一棟一棟一軒一軒の建物所有者が、低予算で無理なく現在の建物を延命出来る事を知る事です。
何ら特別な事ではありません。ビルの本場ヨーロッパをはじめ世界中の街では、それが「当たり前」の姿です。そこに私達日本の街の将来があります。
必要なのは、まず現在の街の建物ありき、現在の街の住民ありき、として現在の街を認め受け止める事です。
そうして無理のない低予算で必要工事を厳選して、さほど費用がかからずにも古い建物が綺麗に維持できるようになれば、低予算で維持ができる建物は、一人一人が広い面積をゆったりと使用する事ができます。ゆとりがある街ができるのです。だから街の人口が減少をしても、一人一人が広い面積を使う事ができます。セカンドルーム・セカンドハウスとして使用する事ができます。私達はウサギ小屋から卒業し、ゆとりがある街として、街は廃れません。
更に古い建物が建ち並ぶ街ならではのローカルルールが育てば、街の魅力を向上させて、自分達の土地の資産価値を上げる事もできるようになります。
もうスクラップアンドビルドの時代ではありません。巨額の投資は不要です。もっと現在の街と現在の街の住民に向き合い、地に足のついた現在の街の持続を考える自治体の方は、ご連絡を下さい。
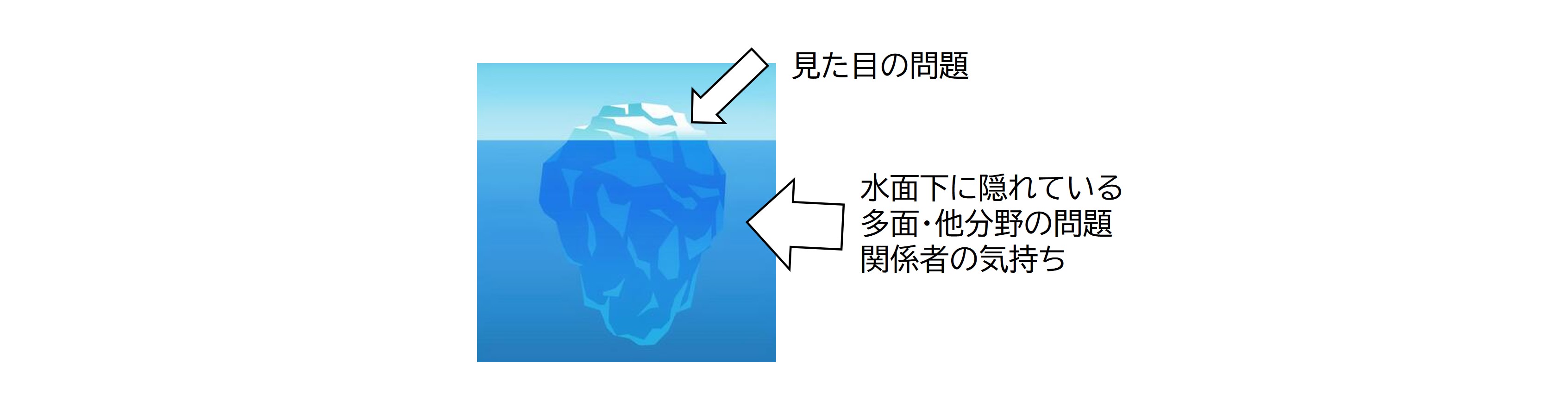


お気軽にフォームお問合せ又は無料オンライン面談をご予約下さい


より詳しくは