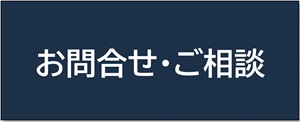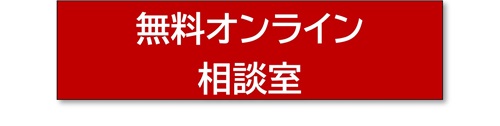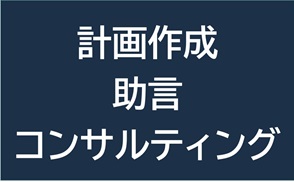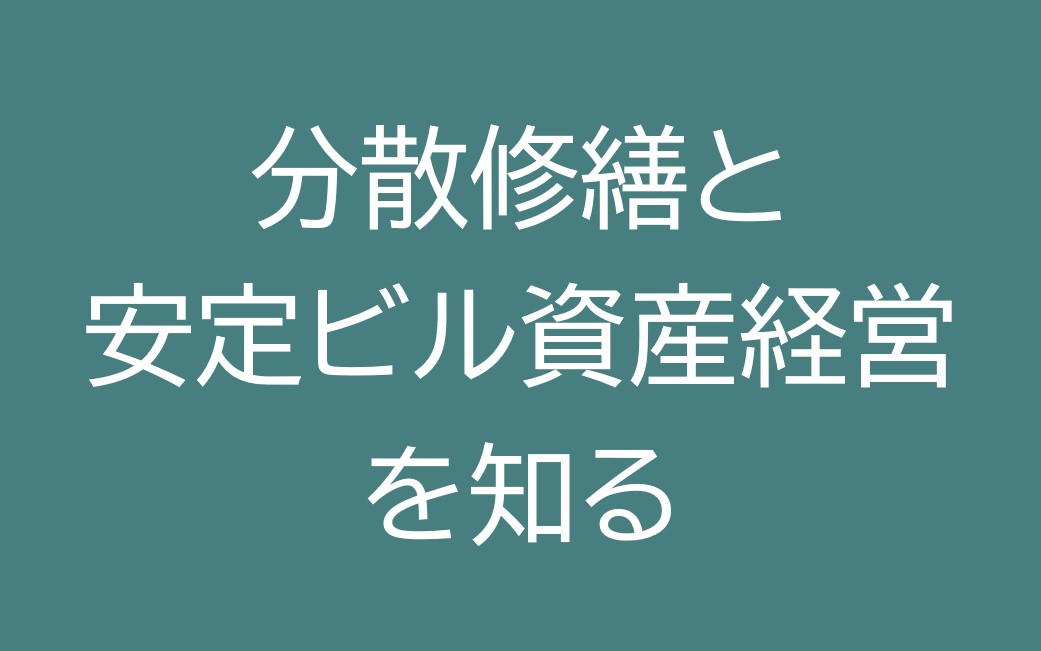築30年以上中小ビル賃貸経営者/後継者のための
.
所有の住宅を、マンションを、中小ビルを、永久資産にする

建替え困難な時代、現在のビルを負債にせず使用利益を有む資産として次世代に引き継ぐ
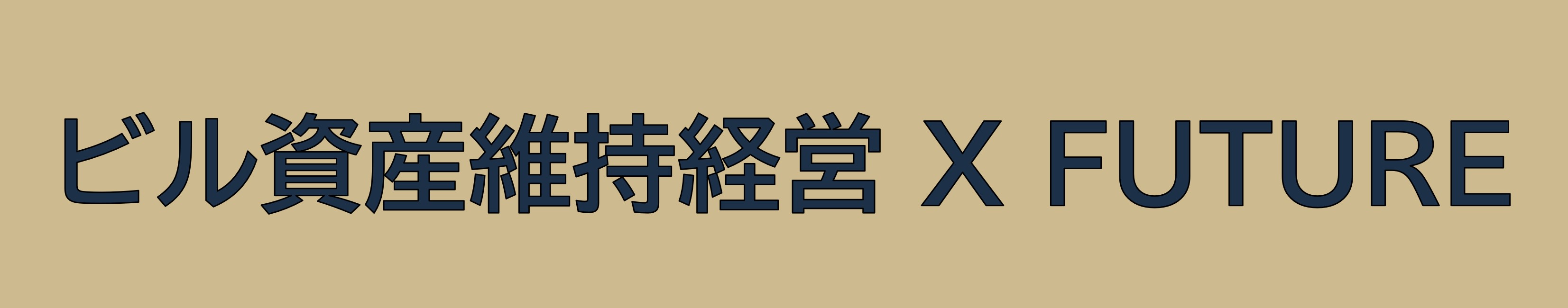
まずどうして私達日本人が今、今までの建築業界頼り、不動産業界頼りから、分散延命を学び自立した建物資産所有者に変わらなければいけないのか、については、こちらでご紹介をしています。
→ 1建物永久資産化が、縮小時代に豊かさを作る鍵
所有建物を永久資産化する分散延命と賃貸も含めた建物資産経営の実践ポイントについて、こちらでご紹介をしています。
→ 2建物を永久資産にする分散延命
→ 3賃貸も継続の安定ビル資産経営
またこうした所有建物を永久資産化するための問題解決取り組みに欠かせない建物資産の3面性について、こちらで簡単にご紹介をしています。
→ 4建物資産の3面性
いずれにしろ、身に着けるのは実践が一番効果があります。築古中小ビル資産所有者・経営者・後継者の方、資産管理会社経営者の方、現在ビル資産の永久資産化を、問題解決と合わせて助言・支援ができます。 管理会社や建設業者とは違う、世界標準の自分の土地と建物資産を守る建物アセットマネジメントによる、全く新しいアプローチを、是非ご体験下さい。
お気軽にフォームお問合せ又は1時間の無料オンライン面談をご予約下さい